序破急を使って構成、章立てを考える
映画の予告を観るような構成を
1973年にデビューし、世界中を席巻したバンド「Queen」。1991年にリードボーカルのフレディ・マーキュリーが死去してからも、残されたメンバーによるクイーン名義での活動は断続的に続いている。僕も高校〜大学にかけてものすごくハマった。そんなQueenの楽曲がタイトルとなっており、フレディ・マーキュリーを描いた伝記映画「ボヘミアン・ラブソディ」が大人気だ。僕はまだ観に行けていないが、、、。YouTubeで予告編を観ると、たしかにこれはワクワクする。観客とともに「ウィ・ウィル・ロック・ユー」を唄うフレディの姿は、まさに全盛期のQueenの映像を見ているようだ。
映画の予告編は、文章を書く時にとても参考になる。と教えてもらったことがある。
文章を書く際、昔は「起承転結」で構成を考えたものだが、今は「序破急」の方が好まれるようだ。本を作るにあたって、構成、章立てを考える場合にも、この「序破急」で考えるといいだろう。

雅楽の序破急が物語を面白くする
序破急はもともと、琴やしょう、ひちりき、琵琶、太鼓といった楽器で演奏される日本の伝統音楽である雅楽の用語である。「序」はゆっくり、「破」は序より少し早くなり、「急」は最も早くなる、このように楽曲が構成されているのが理想的だという。序破急をイメージするために分かりやすいのが、前述の映画の予告編やTVCMだ。
■序
作品の開始や導入部。起承転結で言うと「起」の部分に当てはまり、序で見ている者を引き込む。物語であれば、簡単なストーリーや登場人物などの説明を済ませて、核となる出来事や事件を発生させておく。
■破
作品において展開や転換が起きる部分。序で引きこんで、破で面白くなりそうだと期待を持たせ惹きつける。起承転結で言えば「承転」の部分に当たる。
■急
作品の結末となる部分。起承転結の「結」。物語であれば、感動や達成感といった部分で、見るものに満足を与える部分だ。ここがうまくいかないと「物語としては失敗」と言える。

本を作る際にこの序破急をどう考えるか?
起承転結ほど章を分けたくない、簡潔にしたい、そんなに文章量が多くないといった場合は、序破急は有効になる。上記したように、序破急は起承転結で言うところの起=序、承転=破、結=急に該当する。本を作る際のそれそれの内容とボリュームの割合は以下のようなイメージである。
序・・・誘引(約5〜10%)
破・・・メインテーマ。解の提示(約80〜90%)
急・・・総括章(約5〜10%)
起承転結と同じく、「承転=破」が読者のニーズに回答する部分に当たるので、破のボリュームが最も多くなる。ただ、単純に三分割するだけでは破の部分が非常に長く、読者も読み飽きてしまうことが想定される。序破急の「破」は、起承転結の「承転」より文量が圧縮されているのが特徴で、
作品の中で決定的な部分までのスピード感があると良い。また、本を作るうえで序破急を使うときは、明確にテーマを打ち出したい時などがおすすめだ。起承転結でよりも、よりストレートにテーマを伝えることができるだろう。
本に書くテーマが決まったら、まずは内容を序破急に当てはめて、映画の予告を作るように考えてみてもらいたい。この映画は観てみたい!と思ってもらえそうか?構成、章立ての段階で是非イメージしてみよう。
関連記事
-
なぜ電子書籍なのか、なぜ出版なのか②
2016/11/24 |
なかなか物事が進まないと気持ちが落ち込んでしまいがちですが、それでもその時間が新...
-
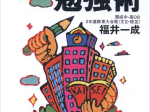
-
本を電子化して世界の読者へ届けよう
2023/01/18 |
「突然著書が絶版になってしまった、、、。なんとか継続して販売できないだろうか?」 時折、私のと...
-

-
どんな本を発信するかが大事
2016/11/09 |
食べ放題も飲み放題もあまり好きではないTakaです。だって、そんなに食べられないし、飲み放題の中に好...
-

-
後世に遺すためのデジタルアーカイブ
2019/02/09 |
東京の都営地下鉄大江戸線若松河田駅を降りて東新宿方面へしばらく歩いたところに、一般社団法人発...
- PREV
- 誰でも出版できる時代 準備を大切に
- NEXT
- セルフブランディングのための自費出版






































