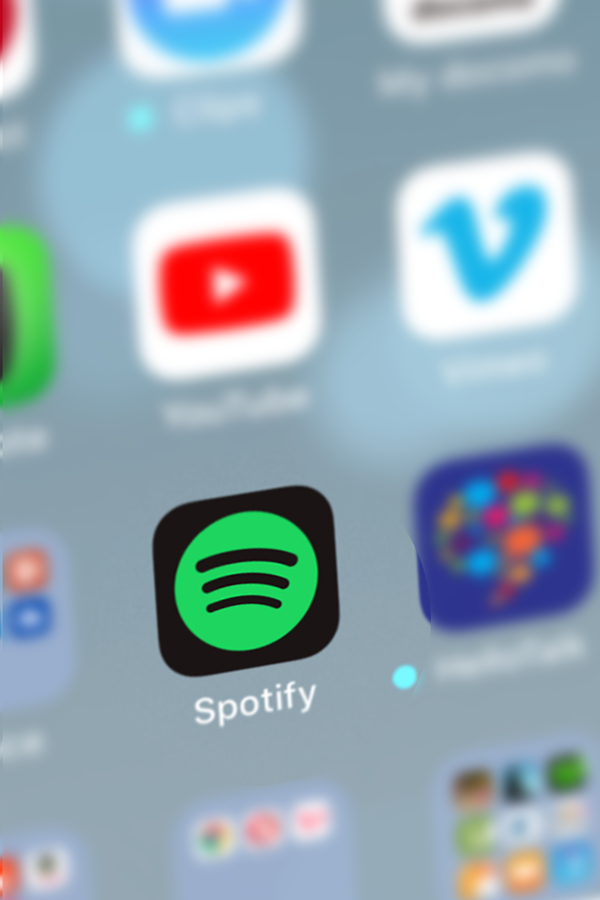来航する数々の黒船に日本の出版界はどう挑むか
本というコンテンツの新しい形が生まれる
2016年11月に、スウェーデン生まれの定額制音楽ストリーミングサービス「スポティファイ」が日本でサービスをスタートさせてから、1年半が経ちます。スポティファイは、会員数が全世界で1億人以上、有料会員だけでも5000万人に達する勢い。配信されている楽曲数は4000万曲以上といわれ、音楽ストリーミングではモンスター級のサービスですね。
僕もiPhoneにスポティファイアプリをインストールして使っています。
日本ではApple Musicが先行して聴き放題のサービスを展開していましたが、後発で日本に入ってきたスポティファイも、有名なアーティストであれば、Apple Musicと同様にほとんど聴くことが可能です。さらに、新しいアーティストとの出会いをコンセプトにしているので、まず各ジャンルのプレイリストがレコメンドされ、プレイリストを選ぶとその中で新しいアーティストとの出会いがあったりします。ジャズが好きな人が、ジャズのプレイリストの中で新しいアーティストの楽曲をストリーミングして好きになる。そんなイメージです。
そのスポティファイが、オーディオブックの配信に乗り出すようです。先日、英国の出版社「Bloomsbury Publishing」が保有する、音楽関連のノンフィクション作品「33 1/3」シリーズの配信権を手に入れ、ストリーミング配信を開始しようとしているという。スポティファイのバイスプレジデントでるCourtney Holt曰く、「熱心な音楽ファンである私は、ずっと以前からこのオーディオブックシリーズに注目していた」とのこと。オーディオブックの配信にあたり「様々なフォーマットにチャレンジする」としていますが、果たしてどういう形式にするのか楽しみなところです。
出版社側としては今回の取り組みで、コンテンツである「書籍」の新しい販売方法が確立され、これまでになかった収益モデルが生み出されることになりそうですね。恐らくはそのサービスの中で、どんどん新しい本との出会いを創出するのではないでしょうか。
続々と来航する黒船に日本の出版界が何をすべきか
そんな新たなサービスに世界が注目する中で、日本の既存出版流通形態に危機が訪れようとしています。
2015年6月栗田出版販売による民事再生法適用申請、2016年2月太洋社の自主廃業発表と、日本の再販制度の中核となってきた取次会社の破綻が相次いで起こっています。取次会社は、電子取引システムやファックスを使って、国内にある膨大な数の出版社から本を仕入れて、全国に数多ある書店に仕分けて配送しているわけですが、在庫管理も困難な小規模出版社からの仕入れなどは困難を極め、すぐに商品を仕入れることが難しくなっているのが現状です。となれば書店への配本も遅れ、書店で本を注文した消費者に、本が届くのが1週間〜10日後になることもしばしば。消費者からの注文に、購入時間がかかる取次ではなく、アマゾンから直接買うという書店まで出ているそうです。
そのアマゾンは、カスタマーファーストを掲げ、欠品率を限りなくゼロに近づけ即日配送まで実現してきたアマゾン。今年2月に開かれた、アマゾンメディア事業本部書籍事業方針発表会では、2017年の1年間で760の出版社が新たにアマゾンとの直取引を導入したと発表しています。直取引の導入出版社数は、累計2300社を超えるとされています。日本の再販制度と取次会社の状況を俯瞰したアマゾンが、栗田出版販売の民事再生法適用申請以来、出版社に直接取引を持ちかけてきた結果でしょう。まさに、日本の出版流通とは真逆の道を進んでいます。
今後はアマゾンのほかにも、前出のスポティファイのような書籍コンテンツの新しい形を生み出すところも多数現れてくるでしょう。旧態然とした仕組みでは出版流通が成り立たない時代が、本当にもう眼前に迫っているのです。
関連記事
-

-
誰でも出版できる時代 準備を大切に
2019/01/08 |
世界中から日本に訪れる留学生たち。日本との縁を感じ、日本に興味を持って、日本語や日本の文化、政治経済...
-

-
そろそろ図書館が電子書籍を導入する時が来た
2016/11/19 |
11月10日EU裁判所が、オランダの図書館がE-Book貸出の合法性確認を求めて提訴していた裁判で、...
-

-
日本の経営者は本を書こう
2019/04/15 |
去る4月12日(金)当社で初めてのビジネス交流会をスタートした。「山元ビジネス塾」と称したこの交流会...
-

-
来たる5Gの時代 デジタルコンテンツの準備はできていますか?
2019/12/19 |
建築業界にもIoTの波がやってきた 先週東京ビッグサイトで開催された住宅・ビル・施設Week 東京...
- PREV
- 世界のどこからでも世界中の本が読める仕組みを
- NEXT
- トモ・タカイの「アール・ブリュットの世界」