作って売るだけでは売れないのが電子書籍
公開日:
:
電子書籍
小学生の頃、毎月、毎週発売されるコミック雑誌を楽しみにしていませんでしたか?
ジャンプ、サンデー、マガジンなど、定番の少年誌。みなさんも買っていたのではないでしょうか。もう少し年少だと、やっぱりコロコロコミックでしょう。そうそう、ボンボンもありましたよね?ボンボン、懐かしい!
今、漫画というとLINEマンガやRenta!などで見ている人が多いのでしょうか。電子書籍の約8割はコミックだというから、結構スマホで読んでいる人もいるんだろうな。電車でもよく見かける。
今日はドラえもん、コロコロコミックで有名な(他にもあるけど)小学館さんへ伺いました。
小学館といえば、1922年創業の出版社で、その名前は小学生向けの教育図書出版を主たる業務としていたことに起因しています。今では、学習誌から雑誌、コミックまで多数のアイテムを揃えています。
今日はその学習誌の一部を電子化するというお話で伺ったのですが、これだけの出版社ですからね、すでに内製で電子化されています。ただ、アイテム数があまりにも多いので、電子化できるもの、できていないものがあります。今回僕がクリエイターEXPOで見せてもらった、躾の本や小学校の特別活動、いわゆる特活の本などは、まだまだ電子化の対象になっていないようなんですね。
実はこの躾や特活って、海外で注目されていると言われています。アメリカなどでも、学校教育ということとは別に、クラブやチームスポーツ、塾などで取り入れるところがあるそうで。
うちのオモイカネブックスから出版された、サムライ先生こと外薗明博さんの著書『国境を越えたサムライ先生』の中でも、日本式の躾がアフリカウガンダの子どもたちの生活習慣を改善し、チームスポーツにおいても成績が向上したという結果を紹介しています。そこで、小学館さんの躾、特活の本を電子化して、海外へ発信してはどうかという提案に行ったわけです。
過去の書籍の電子化については、内容の再精査、写真の撮り直しの必要性などもあり、すぐには進められなそうというのが結論ですが、お話の中で僕たちの事業内容で特に興味を示して下さったポイントがあります。それがどこかというと、一つは「海外発信」もう一つが「著者プロモーション」
海外への展開でいえば、それこそドラえもんの英語版が100冊以上出版されていて、kindleで売られているそうです。でも、あまり売れ行きが良くないとのこと。良くないと言っても桁が違いますが、天下のドラえもんですからね、もっと売れていてもいいのかな?と思う数字でしたね。それ以外にも英語版を出しているものがありますが、軒並み売れ行きが悪いようです。
Kindleはあれだけのユーザ数とアイテムボリュームを持っていますからね。アップすれば売れそうだけど、まず売れないですよね。アップするだけだと、小学館のような大きな出版社の本も、なかなか売れないわけです。ましてや自費出版物が爆発的に売れるというのは、割と奇跡ですよね。
だから、著者(著書)のプロモーションが大事になってくる。紙の本で言われてきた、再販制度があるから出版社はプロモーションに力を入れなくてもいいという話、たしかにそういう側面もあると思うけど、出版社さんだって売れた方がいいに決まってますよね。出版社の中のみなさんは、一所懸命売ろうとしている人がたくさんいますよ。
電子書籍だと再販制度はないから、とにかく売れるに越したことはない。だからプロモーションしたいけど、人的リソースと、時間が足りないそうです。みなさん忙しそうですもんね、、、。
電子書籍業界のポイントはここにあると、改めて思いました。そして僕たちが進もうとしている方向性は、間違っていないと。ともかくも著者をプロモーションして、著者のことを知ってもらって、エンパワメントすることが、電子書籍時代の売れる仕組みにつながると思う。ドラえもんで育てられた僕ですから、是非とも小学館さんの販促の役に立って、恩返ししたいと思います。
まずは、世界への発信というところを、もう一度考え直さないと!
あーー、ホンヤクコンニャクが欲しいよ、ドラえも〜〜ん!!
関連記事
-

-
主体性を育むフィンランドの子育て
2019/06/24 |
主体性を育む子育てとは 主体性と自主性の違いは何か? よく聞く言葉だが、明確な区別をせずに使って...
-
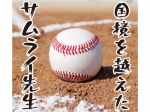
-
電子書籍を出版する⑤ デザイン
2017/09/10 |
電子書籍のデザインというと、まず必要なのが表紙です。...
-

-
電子書籍はもう読まない!?
2015/10/12 |
電子書籍は買いますか? 僕は紙の本も買いますが、kindle storeのデータ...
- PREV
- あなたにとってのメリットを教えてあげるのが大事
- NEXT
- 音楽が導く世界の相互理解








































