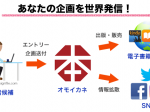図書館はよりコミュニティスペースに
鹿児島県東部に志布志市ってありますね。
あの、「養って」って動画で炎上?した市です。市役所の支所の表記が「志布志市志布志町志布志の志布志市役所志布志支所」ってことでもネットで話題になっていますね。文字数が長いということであれば、千葉県市川市にある市川小学校も、「市川市市川二丁目三十二の五市川市立市川小学校」という住所表記。長いね。
まあそれはいいとして、その志布志市に小さな絵本図書館がオープンしたというニュースがありました。
店主である西岡さんが、海外生活の中で子どものために集めた絵本約700冊を陳列したもの。700冊の絵本ってすごいですね。海外生活の中でってことなので、おそらく絵本の中身は現地の言葉でしょうね。何語で描かれたものがあるのか見てみたい気もします。
こういう本ってすごく貴重だと思います。なかなか日本国内、ましては都心部でなければ見る機会ってないですからね。もちろんamazonで買えないことはないでしょうけど、そもそも探さないでしょうしね。絵本って絵が主役だから文字が読めなくてもなんとなく描いてあることはわかる。子供たちは絵を見るだけで楽しめると思います。
リアルな図書館はコミュニティスペース化するといい
図書館というと、決まって思い浮かぶのが物音一つせず、シーンとした環境で本やノートのページを捲る音だけが響く状況。ちょっとでも物音立てたりすると、キッと睨む人がいる。まあ、今はスタバが併設されたりして随分イメージは変わってきているけど、大体が昔と変わらない感じですよね?公立の図書館ではなかなか難しいけど、音楽が流れて、飲食が自由で、おしゃべりもできる。楽しみながら本に触れる図書館があるといいなぁと思う。核家族化が進む中で、学童保育などと同じような役割を果たすような図書館があるといいですよね。今回の西岡さんの絵本図書館は、中国語・英語教室兼物品販売店舗を併設しているということで、こういった店舗が地域のコミュニティになるのではないかと思う。
紙と電子を融合させて新たな価値を
様々なモノのデジタル化が進み、いろんなものがインターネットに繋がる昨今。まだまだ市場は大きくないものの、本のデジタル化もどんどん進んでいます。それでもやっぱり絵本を捲って読むっていう体験は大事だと思う。だから紙と電子を融合させていけたらいいですね。読む場所として、またコミュニティスペースとして図書館を位置付けて、中で提供されるコンテンツは紙か電子を選べるようにしてもいいですね。そこで読むのは紙、借りて行くのは電子版にすれば、スマホやタブレット一つあれば簡単に持ち帰れますからね。
年の初めから様々な新しい技術が発表されています。
新しいアイデアを今まであったものと融合させて、新たな価値を生み出していく。今後の本のあり方でも、新しい価値を考えていきたいですね。
関連記事
-
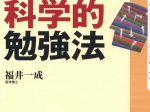
-
あなたの勉強法は間違いだらけ!?大人のための科学的勉強法
2019/07/20 |
あなたの勉強法は間違いだらけ! 勉強法のスペシャリスト“ドクター福井”こと福井一成氏が教える、最新脳...
-

-
デジタルが実現する絵本の世界発信
2018/05/12 |
今月2日、戦後日本の創作絵本をリードした加古里子さんが92歳で亡くなられました。 1967年の...
- PREV
- 人のストーリーをカタチにしよう
- NEXT
- 人の物語を世界へ、そして未来へ