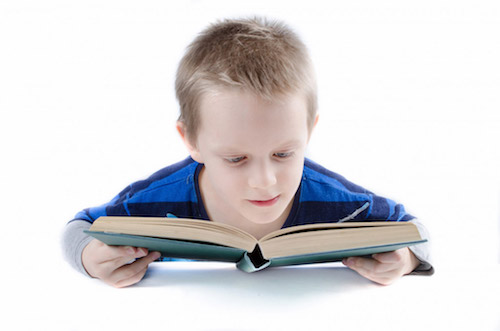電子書籍がもたらす「不」の解消
「ディスレクシア」という名前を聞いたことがありますか?
ディスレクシアとは、通常、会話(話し言葉の理解や表現)は普通にでき、知的にも標準域にありながら、文字情報の処理(読み書き)がうまくいかない状態を言います。知的に問題はないものの読み書きの能力に著しい困難を持ち、充分な教育の機会があり、視覚・聴覚の器官の異常が無いにも関わらず症状が現れた場合に称します。日本でもディスレクシアの人が人口の5%から8%はいると言われています。欧米では10%から15%だそうです。
ディスレクシアの人は、文字が覚えられない、読み方がたどたどしい、読み飛ばしや勝手読みが多い、話せば理解できるのに自分で読んで文字から理解することが難しいといった状況を示します。全く読めないわけではなく、読むスピードがとても遅く、間違いも多いため、学年レベルの文章の読みにつまずき、小さい「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」のようにつまる音や「こう」「よう」のようにのばす音などの読み誤りが目立つそうです。基本的な学習に問題がないために、学校では怠けていると見られて、辛い思いをする子も多いようです。さらに、初めて見る文章は読み書きが困難なために、テストでは良い点が取れず、進学が難しくなってしまうことも。
そんなディスレクシアの支援に効果的なシステムとして「DAISY」があります。DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されています。
ディスレクシアの他、視覚障害者の人々のためのデジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム(本部スイス)により開発と維持が行なわれている情報システムです。アメリカやスウェーデンの録音図書館などではディスレクシアへの録音図書のサービスが行われているそうで。マルチメディア化したDAISY図書だと、音声とテキスト、画像を同期させることができるので、音声を聞きながらハイライトされるテキストを読み、合わせて画像を見ることができます。
これまでは、DAISY図書を制作することが特殊な技術を必要とするものだったと思います。電子書籍の規格がePUBに落ち着き、ePUBデータが容易に制作できるようになった昨今、DAISY図書のようなデータを制作することは一般的になってきたと思うんですね。
僕は電子書籍が持つ可能性は色々あると思っています。販促でも、広告でも、情報発信でも使えると思うし、もちろん娯楽としても楽しめるものだと思います。でも、もっと可能性を秘めているのは、誰かの「不」の解消ではないかと思っています。デジタルだからこそ出来ることが、「不」の解消になるのではないかでしょうか。誰のどんな「不」を解消できるか、いつもそれを頭に入れて電子書籍に携わっていきたいですね。
関連記事
-

-
ボールはともだち。人々もともだち。
2017/05/13 |
キャプテン翼 南葛小のメンバー(wikipediaより) 「キャプテン翼」 ...
-

-
電子書籍利用者5000人超に聞いたみた意識調査
2020/06/19 |
BookLiveは12日、運営する総合電子書籍ストア「BookLive!」の会員を対象に「電子書籍に...
-

-
学習環境の多様化と電子書籍の活用
2018/02/04 |
「ステップアップ塾」という無料塾があります。 2014年に開塾した、学びたいのに家庭環境により...
-

-
結構便利!紙と電子の使い分け
2018/07/13 |
ついに紙と電子を使い分けが始まった 大日本印刷(東京都新宿区)などが運営するハイブリッド型総合書店...
- PREV
- 読み聞かせは最高のコミュニケーションツール
- NEXT
- 「本」の未来を考えなければ