教科書・教材のデジタル化に思うこと
公開日:
:
電子書籍
北欧諸国などで採用されている「Bring Your Own Device(BYOD)」
ご存知ですか?
子供たちに自宅のスマホ・タブレットなどのデバイスを、学校へ持参させるという方法です。
情報通信技術を学校教育で利用するにあたり、すべての子供に国からデバイスを配るとなると、とてつもない予算が必要になりますね。そこでBYODにすれば、利用できるデバイスが無い、ブロードバンド環境の無い家庭だけを対象にできるというわけです。
「デジタル教科書の普及はBYODで」(ハフィントンポスト)
こちらの記事もありますが、スマホ・タブレットの保有率は高くなってきており、デバイスの種別がまちまちでも、デジタル教科書側のコンテンツ開発次第で互換性のあるものに出来るから、特に専用の物を学校側で配る必要は無いってことです。今後はますます教科書もデジタル化が進むのでしょうね。
しかしこれってセキュリティとかどうなのでしょう?インターネットを介するとなると色々心配ですね。そもそも教科書の配信はどこどうやってするのか?それによってはウイルス、ハッキング、情報漏洩などのリスクも伴ってくるでしょう。自前のデバイスだったら尚更怖い…
また自前のデバイスとなると、インストールされているアプリも違うでしょうし、SNSなんて授業中に使い放題ですね。(今でもそうかな?)まあそのあたりの対処法は考えられているのでしょうけど、結局何かと問題が噴出しそうな気がします。
何でもインターネットに繋げるのは便利かもしれませんが、その分様々なリスクが伴うことを使う側が認識しておく必要があると思います。(耳にタコなほど聞かれる言葉ですが敢えて)
BYODの場合は特に気をつけないといかんですよね。
そこでインターネットを介さない教科書・教材配布のシステムの必要性を感じているのです。学校はインターネットにつながることが前提となっている日本や北欧諸国などは良いとして、どこに行ってもインターネットが繋がらない地域もあるわけで。そういった地域でも、同様にデジタルでの教育が可能な環境を整備する必要があると思っています。
記事の終わりにある「バウチャー制度」
そもそもは「引換券・割引券」という意味合いですが、これを教育に活用するというものです。
以前意見交換をさせて頂いた、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンさんが教育バウチャーの配布により、国内の教育支援を行っています。「大阪市の塾代助成制度というユニークな制度」というのが当にチャンス・フォー・チルドレンさんが共同運営するものです。
教育バウチャーの具体的内容については、チャンス・フォー・チルドレンさんにお任せしましょう。
僕たちは、このバウチャー制度にデジタルの技術を取り入れて、より使いやすいものに出来ないか?ということも考えています。インターネットを使わなくても、今の教育環境の効率化や改善が出来て、尚且つ安全性が保たれる。そんなアイディアと技術開発が必要だと思うのです。
関連記事
-

-
電子書籍を出版する④ 文章のルール
2017/08/28 |
文章を書く際、基本的な作文の決まりがあります。 最低限のルールに沿って、...
-

-
電子版中古本市場が電子書籍ユーザーを拡大させる?
2020/07/16 |
昨日久しぶりに書店に行きました。ショッピングセンター内に入っている大型書店です。時間がなかっ...
-

-
さあ、世界を楽しませよう!
2017/04/27 |
ORINOVIVOという音楽ユニットがあります。 ツインパーカッションに、尺八、ギター、ヴァイ...
-
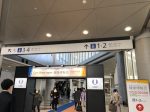
-
日本の技術と心を電子書籍で世界へ発信
2019/01/25 |
日本の技術の粋が光る介護産業展 国の成長戦略の一環として、健康寿命延伸産業の活性化に向けた取り組み...
- PREV
- 本を読んだら運賃無料!?
- NEXT
- 電子書籍はもう読まない!?







































