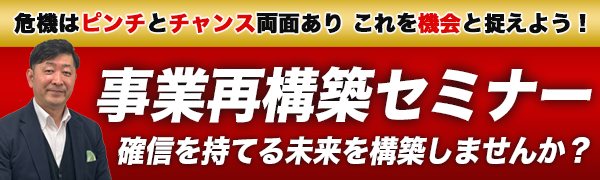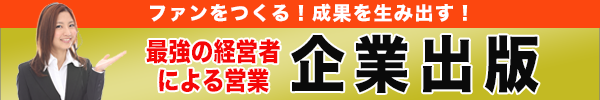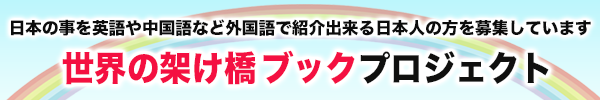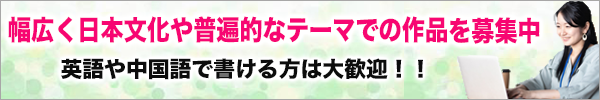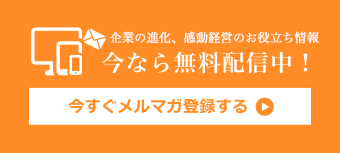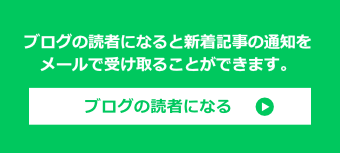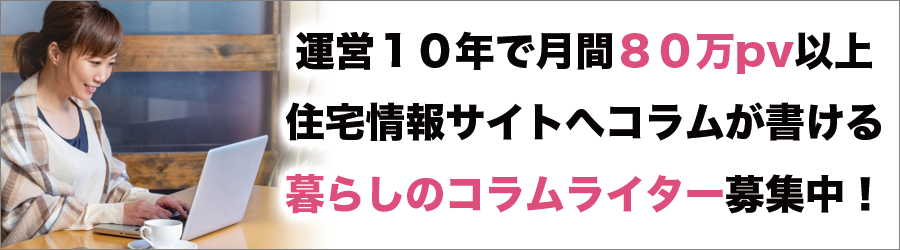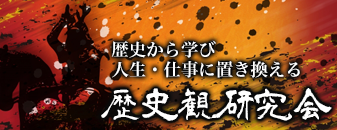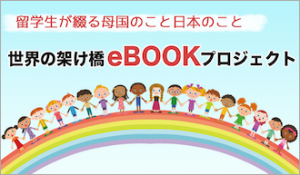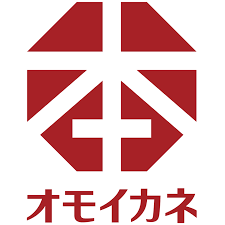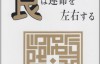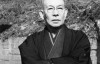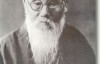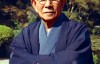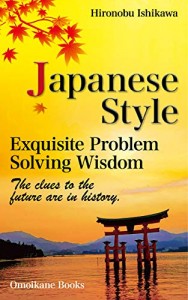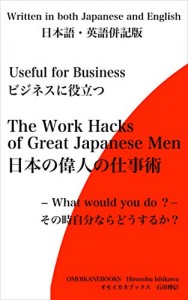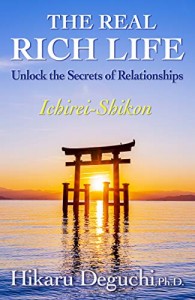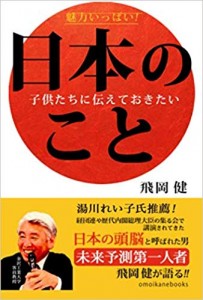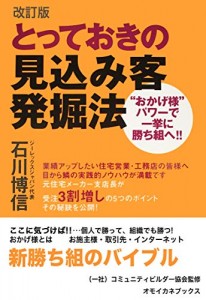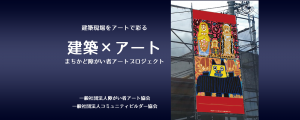日本文化の美意識 ドナルド・キーンの視点
公開日:
:
最終更新日:2025/04/22
未分類
日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」と美意識を読み解く
はじめに:日本文化を探る旅への誘い
私たちが「日本文化」と呼ぶものは、
どこから始まり、どこへ向かっているのだろうか。
二つの重要な書物を軸にこの問いに迫る。
一つは『日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く』が提示する文化的構造の分析。
もう一つは、ドナルド・キーンによる『日本人の美意識』が照らす、
日本人の繊細で重層的な感性である。両書を対話させることで、
文化と美意識の結節点を可視化し、日本の精神の核心をあぶり出していく。
柱を立てる:
見えないものを立てる行為 神社の「柱」は、
空間に意味を与える日本的信仰と美意識の象徴である。
キーンは「空間に対する日本人の鋭敏な感覚」を評価し、
それが建築や庭園、日常の所作にまで及んでいると指摘する。
見えない神を感じ取る行為にこそ、日本文化の始点がある。
受容と融合:
変化を受け入れる力 日本文化の特徴として、
他文化を積極的に取り入れ、独自に再構成する柔軟性がある。
和魂漢才、本地垂迹、さらには明治以降の西洋文化の吸収まで、
すべてがこの「同化能力」によって可能となった。
キーンはこの点を「表面的模倣に見えて、内実は深い再構築である」
と喝破した。彼にとって、
日本文化は常に「異質なものを自己化する」洗練された方法論をもっていた。
祈りと実り:
コメに込めた命の思想 稲作を中心に形成された日本人の信仰構造は、
「祈り」と「実り」を不可分のものとする。コメを供える行為は、
自然への感謝であると同時に、日々の営みそのものへの美的昇華でもある。
キーンは日本人が「日常に聖性を見出す民族」であるとし、ここに美意識の根源を見た。
無常と習合:
儚さの中の美 桜、落葉、夕暮れ。すぐに過ぎ去るものにこそ美を見出す感性。
「もののあはれ」は、キーンが最も心打たれた日本語であり、
その意味を解明するために『源氏物語』を何度も訳したという。
神と仏の融合においても、「矛盾の否定ではなく共存」が日本人の心の核にあると彼は語っている。
和する力、荒ぶる力:
バランスの美学 「和」は秩序の象徴である一方、「荒ぶる」は混沌の力である。
祭礼、神楽、能などに潜む両義性は、
キーンの言う「抑制された激しさ」と通底する。
沈黙の中に燃える情熱——それが日本的な美であり、日本芸術の根源にある緊張感である。
漂泊と辺境:
都落ちの詩学 都を離れ、自然に身を投じることに美を見出す。
西行、芭蕉、『源氏物語』の浮舟。キーンはこの「漂泊の感性」に、
日本人の自己解体と再創造の契機を見た。中心から離れることで、
むしろ核心へ至る。これは西洋的ヒロイズムとは異なる、日本的自己完成の道である。
型・間・拍子:
時間芸術としての日本文化 型があるからこそ自由がある。
能や茶道、俳句など、形式の中に生まれる創造性。
キーンは「日本人は時間を詩的に扱う」と述べ、
七五調のリズムに日本語の音楽性を見出している。
間(ま)の美学もまた、西洋にはない独自性である。
小さきもの:
ミクロに宿るマクロ 盆栽、和菓子、工芸品──小さなものに宇宙を見る感性は、
日本美の核心である。キーンは「細部への執着が全体への美意識につながる」
と述べ、そこに精神的な緊張を感じ取った。見落とされがちなものにこそ、真実がある。
まねびからまなびへ:
模倣の哲学 日本文化では「学び=真似び」。まずは徹底的に模倣し、その中から本質を掴む。
キーンは、弟子が師の動きを一挙手一投足真似る芸道の世界に感銘を受け、
「継承と創造の間に日本の未来がある」と語った。
おおもとへ還る:
循環する文化 文化は直線的に進化するのではなく、
常に「原点」に立ち返る。キーンが強調したのは、日本文化の「反復による深化」である。
何度も同じことを繰り返す中に、微細な差異と新しさが生まれる。
かぶき者の精神:
逸脱することの美 「かぶく」は単なる奇抜さではない。
規範の外に出ることで、新たな価値が創造される。
バサラ、伊達、粋といった言葉には、「自らを表現することこそが生き方である」
という思想が宿る。キーンは、江戸の町人文化にその自由な表現の頂点を見た。
市と庭:
都市と自然の共存 市は商業、庭は自然。
これらが都市の中で一体となることが、日本独自の都市美学を形成する。
キーンは京都の町並みに見られる「経済と精神性の共存」
に驚嘆し、これを「共鳴する構造」と評した。
ナリフリをかまう:
装いの哲学 「粋」「通」「伊達」などの装いの美学は、
外見の問題ではなく、内面の表現である。
キーンは「日本人は服装で思想を語る」とまで述べ、
スタイルが哲学と直結している点に驚いたという。
笑いと風刺:
庶民の批評精神 狂言や落語に見られる風刺の精神は、
笑いを通じて社会を相対化する装置である。キーンは、
落語のユーモアを「知の形式」として捉え、
庶民が持つ美的判断力と精神的洗練を高く評価している。
経世済民:
倫理としての美 商いとは、本来「世をおさめ、民をすくう」行為である。
日本の商人道には、美意識と倫理観が重なり合っていた。
キーンはこの価値観を「美の倫理」と呼び、
グローバル資本主義に対する対抗軸として重要視した。
面影を編集する:
記憶と再構成の技法 面影とは、過去の記憶を現在において再構築する感性である。
キーンは『源氏物語』の描写にこの
「時間の編集力」を見出し、それが日本人の物語性と創造力の原動力だとした。
おわりに:
生きられる美、進化する文化 日本文化とは、
単なる伝統ではなく「生きられる美」である。
形式、融合、逸脱、細部へのまなざし——それらは変化し続ける文化の核であり、
未来へと引き継がれるべき美意識の結晶である。
ドナルド・キーンの深いまなざしと、
日本人自身による再発見が、これからの「ジャパン・スタイル」を形づくるだろう。
いかがでしたか。
ドナルドキーンの考察、深いと思います。
もちろん、意見はあると思いますが、日本文化全体の捉え方として
学べるところがありますね。
石川博信
最新記事 by 石川博信 (全て見る)
- 日本文化の美意識 ドナルド・キーンの視点 - 2025年4月22日
- 言霊の思想 - 2025年4月15日
- あなたが変わる315の言葉 面白い本です - 2025年4月8日
セミナー・研修情報
*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。
●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから
●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます
友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
関連記事
-

-
7月29日新月に祈りを
2022/07/30 |
月の力は偉大ですね。 目標を立てたり、新しいスタートを始めるのに最適だと言われています。 自...
-

-
ビジネスの販促で本をつくってみませんか?
2016/12/10 |
出版企画創ってみませんか? ビジネスに本って役にたちます。 自費出版や商業出版と大きく分けて...
-
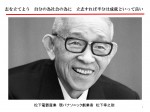
-
経営 哲学 名言 松下幸之助
2019/01/24 |
経営哲学の名言 松下幸之助は多くの名言を残した。 松下幸之助は、著書も多くありその経験を多くの...
-

-
2019年経済予測 社会環境への対応
2018/12/08 |
これから起きる経済津波 飲み込まれるか? 波に乗れば凄い力になる 2019年:消費増税後の住宅...
- PREV
- 言霊の思想