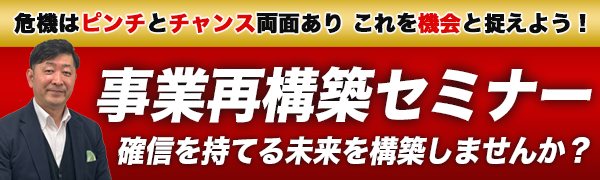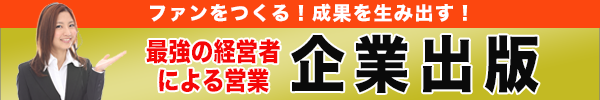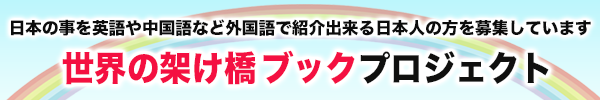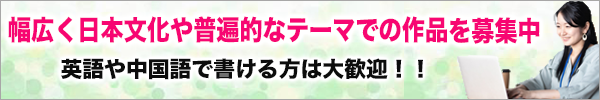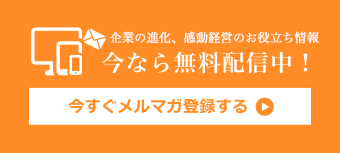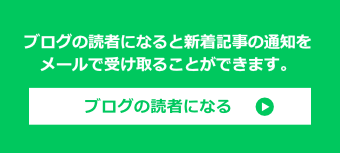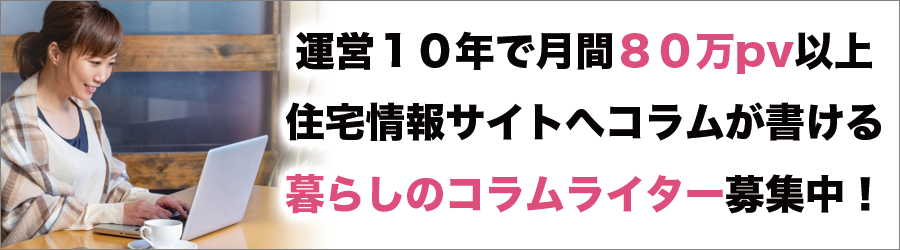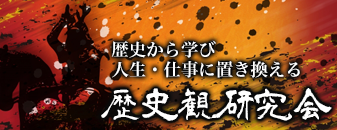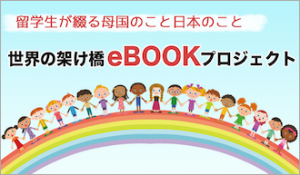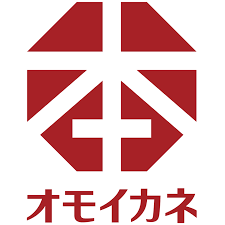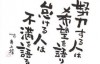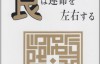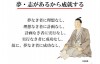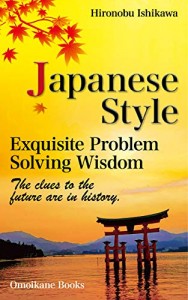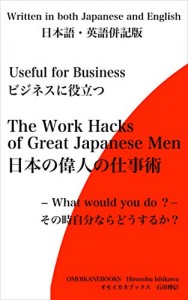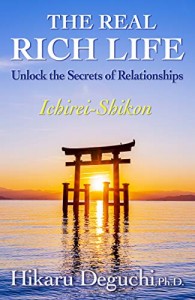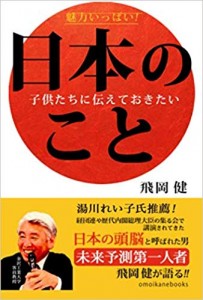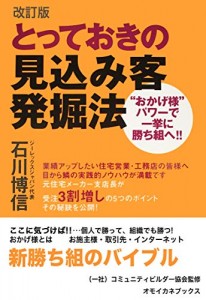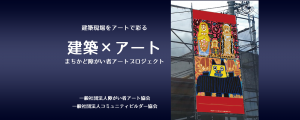七夕の起源はなんだろう
公開日:
:
最終更新日:2017/07/07
巡礼記
仙台七夕祭りの様子 物凄くにぎやかです
なんとなく、七夕っていいなって思いますけどどうでしょうか?
私も子供のときには竹に願い事書いてくくりつけていたものです。
でもなんで「七夕」を「たなばた」って読むんだろう?って素朴な疑問が
合ったりしていた。
ちょっと調べてみると、元々は「しちせき」とよみ節句の一つの時期で
あるそうです。
節句は1年で5回あり、
1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日とありますが、
で、なんでたなばたって良むかというと「棚機」(たなばた)と読む。
日本では平安時代に始まったそうで、最初は宮中行事で行われていましたが
江戸時代になると庶民にも伝わり、五節句の一つとして全国的に広がるように
成りましたが、短冊に色々な願いを書いて笹の葉につるすというやり方も
この頃から盛んになったそうです。
これが一番関連があるかなと思う。
7月7日の「たなばた」は神道の禊で乙姫が着物をおって棚に添えて
神様を迎えて秋への豊作を祈ったり、穢れをはらうという儀式だったそうです。
選ばれた乙姫(ちいきで選ばれていた)は川の水で清めてこの儀式に当ったという。
おりひめとひこぼしの物語が有名ですが、おりひめとひこぼしですが
ベガとアルタイルとい二つの星は天の川をはさんで最も光り輝いているように
見えるということから中国ではこの日を一年に一度のめぐり合いの日と考え
七夕のラブストーリーが始ったとも言われています。
七夕に限ったことではないけれど、日本人のアレンジ力は凄いなって思う。
やはり暦とも関連があると思うけど、それをお祭りに変えていってしまう。
更に、子供も参加できるような形にかえていって
大人だけでなくて、子供も参加できるようにしていく。
実は、日本にはこのようなお祭りとか行事とか一杯ある。
なんで、日本人は基本あかるく、お祭りすきっていうのはあると思う。
にぎやかなのがすきなんですね。
で、このようなお祭りとか行事がなんとなく生活のリズムの文字どうり節目に
なっていってしまうという。
面白いですね。
そしてこのようなお祭りであっても、季節感や自然との調和ということも
自然に出来ているともおもう。
七夕でつかう竹も古来では神聖で、神道でも結界を作ったりするときに
つかったり、かぐや姫のように竹から生まれるというくらい
竹に対しての神聖さを感じていて、そこに願いを込める、
そして「オリヒメとひこぼし」が無事あえるように
と願っていく。ここでも自分のためでなく
主役の二人の祝福を願うって凄いですね。
ここには、自分がないから。
と・・おもったらやっぱり自分の願いも笹の葉に短冊につけて
一緒にお願いしている(笑)
きっとこれは庶民に広がる過程でできたものでしょう。
面白いですね、日本のお祭りや伝統行事は。
石川博信
最新記事 by 石川博信 (全て見る)
- 日本文化の美意識 ドナルド・キーンの視点 - 2025年4月22日
- 言霊の思想 - 2025年4月15日
- あなたが変わる315の言葉 面白い本です - 2025年4月8日
セミナー・研修情報
*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。
●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから
●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます
友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
関連記事
-

-
斉藤一人さんの言葉 仕事の向こうに見える笑顔の数で成功は決まる
2022/03/03 |
2022年幕張メッセで行われたスーパーマーケットトレードショウ 全国の食文化でも比較的新しい食...
-

-
三つ鳥居の神社 京都の蚕の社 墨田区の三柱鳥居と三井家
2017/04/10 |
木島坐天照御魂神社 このしまにますあまてるみたまじんじゃ 三つ鳥居の神社 京都にある蚕の社とし...
-

-
巡礼記 世界初の御酒を訪ねて 久留里編
2016/05/03 |
当社のファイティングユキと記念撮影 GWいかがお過ごしですか? 私は別名、G(がんばる)...
-
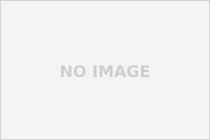
-
自己探求から自分を明らかにする
2016/04/15 |
何故この仕事をしているか?お客様が自社に頼む理由は何か? ここをしっかり自分自身でも捕らえておくこ...
- PREV
- 吾、唯、足るを知る 竜安寺のつくばいの心
- NEXT
- 地酒自動販売機 仙台駅ビルにある